1 薬用部位を知ること
| 薬草は経験的に用いる部位が決まっています。根、根茎、根皮、葉、全草(地上部全部)、つぼみ、花、樹皮、つる、果実、種子、仁など薬草によって特定の部位を使用しますので、これらを知っていないと効かない、効きすぎて毒性が出るなど不都合が起きる可能性があります。薬用部位の例を挙げます。アケビの薬用部位はつるです。モモの薬用部位は種子の核の中の仁です。コブシはつぼみを用い、ベニバナやカミツレは花を用います。シャクヤクは根を用い、タラノキは根皮、キハダやトチュウは樹皮を使用します。 |  |
天然の毒から身を守る
【薬草について】
薬草を用いるときの注意
1 薬用部位を知ること
薬草は経験的に用いる部位が決まっています。根、根茎、根皮、葉、全草(地上部全部)、つぼみ、花、樹皮、つる、果実、種子、仁など薬草によって特定の部位を使用しますので、これらを知っていないと効かない、効きすぎて毒性が出るなど不都合が起きる可能性があります。薬用部位の例を挙げます。アケビの薬用部位はつるです。モモの薬用部位は種子の核の中の仁です。コブシはつぼみを用い、ベニバナやカミツレは花を用います。シャクヤクは根を用い、タラノキは根皮、キハダやトチュウは樹皮を使用します。
2 前処理方法
薬草を用いるときはほとんどが乾燥させてから必要量を用います。民間薬としては生の葉等を用いるものもあります。昔は冷凍・冷蔵保存の方法がなかったため、薬草は春夏秋冬いつでも使用できるように保存のために乾燥させておくことが基本でした。つまり、乾燥したもので経験的に何に効くか薬効を見つけ出したのです。
乾燥した薬草を600mlの水で煮詰めて半量(300ml)になったところで布で濾(こ)してから、熱いまま又は冷めてから1日3回100mlずつ服用します。通常の方法から外れたやり方では危険を伴うこともありますので気をつけてください。例えば、生で食べたり、青汁にしたりするものは通常の薬草の用い方ではありません。焼酎に漬けて薬用酒にするものも作用が強いものは避けたほうが無難です。
3 服用する量の間違い
作用の強い薬草は服用する量を間違うと下痢や腹痛その他の作用が出ることがあります。薬草を用いるときの大まかな量は決まっていますが、病院で処方される薬のように厳密なものではありません。これらの薬は医師・薬剤師によって用法用量が管理されているのでこれを守っていれば健康被害にあうことは滅多にありませんが、薬草は自己管理になりますので自分にあった用量を見つけ出すことが大切です。一般的には薬草の目安の用量がありますので、それより少ない量から始めると良いでしょう。
4 毒草との区別
毒性のある植物は覚えておくことが必要です。薬用でも毒に近いものがたくさんあるので、使用するときには専門家にきくことが第一です。例えばジキタリス、ハシリドコロ、フクジュソウ、トリカブト、スズラン等を薬草として取り上げている本もありますが、使用法が難しく、ひとつ間違えば命にかかわるので、これらは使用しないでください。特別な処理を施さない限り毒草です。
5 薬効の認識
薬草は身体によいといっても作用が強いもの、弱いもの、ほとんど効かないものなど段階があります。用いる量の問題もありますが、ここでは薬草を適切な用量で用いたと仮定して考えてみます。薬草の効能・効果は以下にあげる1〜9などの場合が考えられます。
以上のような実情を知らないと"効く"と言ってもどのレベルなのか認識できません。どの段階にどの薬草を位置づけるかは専門家でも難しいものがあります。1〜4では経験的に薬効が考えられるものもありますが、科学的証明はされていないものも多く、一律に効能効果を言う事は難しいと考えます。5〜8は科学的根拠に基づきますが、専門家でなければ評価は難しいでしょう。正確な情報の解釈が必要です。一つ一つの薬草の解説は他の機会に譲りたいと思いますが、このような情報を持たず安易に薬草を用いると健康増進どころか健康被害にあう可能性がありますので気をつけましょう。薬草をうまく使うには専門的知識、詳細な情報が必要です。
- 『神農本草経』、『本草綱目』など中国の古い医薬の書物に記載されている薬効
- 陰陽五行説に基づいて薬効を推定したもの
- 経験を基に古い書物にまとめられた薬効
- 経験的に長い間用いられてきて確立した薬効
- 動物実験で効果が認められた薬効
- 有効成分が明らかになって効果を推定しているもの
- ヒトの細胞を用いて作用を確かめているもの
- ヒトでのデータのあるもの
- ヒトでの臨床データがあり有効性の検討がされているもの
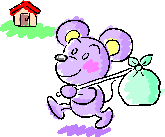
現在の薬草の位置づけは健康保持増進・疾病予防に用いることが適当と考えられます。病気の人は薬草を用いて治すということではなく、医療機関を受診し、医師による診断と適切な治療を受けることが必要です。